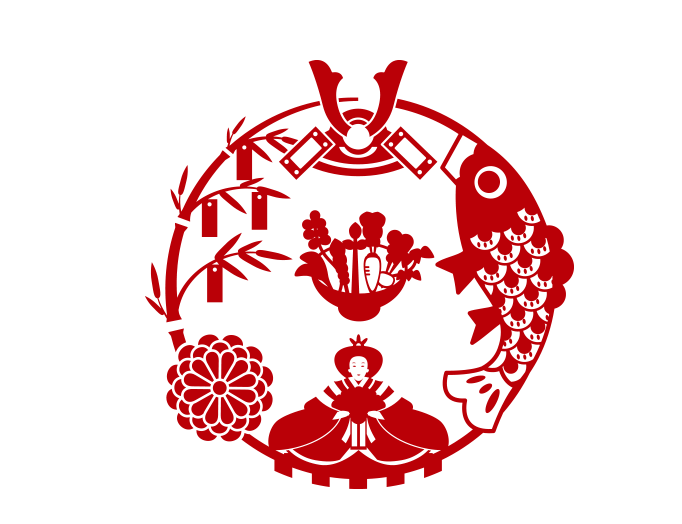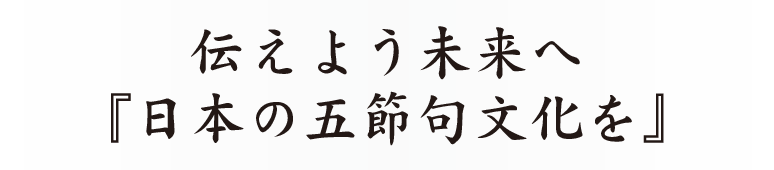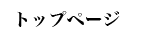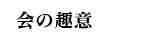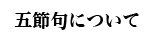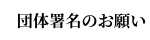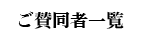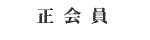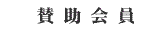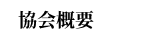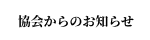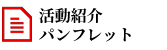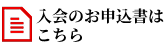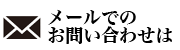協会からのお知らせ
日本の節句文化を継承する議員連盟(仮称)設立に向け打ち合わせ会
日本の節句文化を継承する議員連盟(仮称)設立に向けた打ち合わせ会が、逢沢一郎代議士を発起人として衆議院第一議員会館にて開催されました。全国各地の先生方や文化庁のご担当者からもご出席賜り、日本が誇る大切な節句文化をどのように次代に継承していくべきか、貴重な意見交換の場となりました。特に、間近に迫った東京オリンピックパラリンピックは、世界に日本を発信する機会であると同時に、自国の文化を見つめ直す好機でもあります。私たち日本の節句文化を継承する会は、先生方からのご指導を賜りながら、今後益々活動の輪を広げて参ります。
(文責)専務理事 柴崎 稔



研修会「無形文化遺産のオモテとウラ」講師:石川道大氏
平成30年6月13日(水)定時総会終了後、同会議室にて「無形文化遺産のオモテとウラ」と題して研修会が開会されました。講師には、石川紙業株式会社 代表取締役 石川道大氏をお迎えし、ご講演頂きました。石川氏は1971年 美濃市に生誕され、倉庫業を経て1998年に家業である石川紙業にご入社、2006年に5代目代表取締役にご就任、『「豊かな日本の心をプレゼント」商品と仕事を通して、お客様の元気、幸せ、笑顔をつくること』を経営理念とされ、本美濃和紙発展の為、日夜ご活躍されています。
本美濃和紙は、2009年にユネスコ無形文化遺産に向け動き出しましたが、当時は国指定の重要無形文化財である必要があったそうです。また和紙では島根県の石州和紙が既に重要無形文化財として登録されており、本美濃和紙との違いなどを明確にしなければならい事もあり、ご苦労なされました。文化庁にも何度も相談し、当時の美濃市長を中心に市も全面的に協力して頂いたそうです。そんな中、本美濃紙だけではなく、島根県の石州和紙と埼玉県の細川紙とでグループ化し、和紙として併記し提案出来るよう互いに協力し、登録を実現されたそうです。そして、2014年に念願のユネスコ無形文化遺産登録を果たされました。
今の登録基準は、違うようですが一つ一つの力が集まり、官民一体となっての努力が実現へと導かれたのだと感じました。
講演終了後、講師の石川氏を囲んでの懇親の場が設けられました。
(文責 小田洋史)



平成30年6月理事会&平成30年度定時総会 開催
平成30年6月13日(水)、大阪商工会議所 会議室にて平成30年6月理事会と平成30年度定時総会が開催されました。理事会では、定時総会に向けて平成29年度の各事業報告と平成30年度の各事業計画(案)について、「日本の節句文化を継承する議員連盟」設立計画(案)、内部広報誌作成事業計画(案)などが協議・審議されました。
定時総会においては、平成29年度事業報告、平成29年度決算報告(監査報告)、平成30年度事業計画(案)、平成30年度予算(案)などが全会一致で承認され、弊会の新たなスタートとなりました。
(文責 小田洋史)


平成30年5月5日 端午の節句
明日、五月五日は端午の節句です。連休を締めくくる日として、端午の節句を楽しみましょう!古来より端午の節句は、厄除けの大事な日でした。鎌倉時代から武家政治へと移り変わり、武士の間では、尚武(しょうぶ=武の精神)の気風が強く、「菖蒲」と「尚武」をかけて、端午の節句を尚武の節目として盛んに祝うようになりました。
江戸時代に入ると、五月五日に男の子の誕生を祝い、武士の精神的な象徴である鎧・兜や幟旗(のぼりばた)などを飾って、その子の健やかな成長と家の繁栄を祈りました。やがて民間にも広がり、大きな作り物の兜や武者人形、紙の幟旗など飾るようになりました。また、外に飾る飾りとして鯉のぼりがあります。その昔、鯉が登龍門という滝を登りきると龍になって天に昇るという伝説があり、男の子が健康に育ち、出世して立派な人になってほしいという願いを込めて飾られました。
男の子が健やかに、たくましく育ちますように、病気や事故なく幸せな人生を過ごせるようにとの願いが込められた飾りは、周りの人たちの温かな想いが形となったものであり、子供の誕生を心から喜び、祝う日本の伝統行事の一つとなって現在も伝わっています。
(文責 広報委員会 小田洋史)

若きチカラ結集!「未来への懸け橋」構築事業 関西地区編 開催
平成30年4月26日(木)、全国の節句人形従事青年層による「未来への懸け橋」構築事業関西地区編が「マイドームおおさか」会議室にて開催されました。昨年秋からスタートした本事業も全国5ヶ所目の開催となりました。当日は、業界の大ベテランがオブザーバーとして見守る中での座談会で、少々緊張感のある進行でしたが、関西の若者らしい活発な意見交換がなされました。参加者の発言にもありましたが、ここで出されたアイディアをいかに具現化していくのかが今後の課題です。若者の柔軟な発想力・行動力とベテランの経験値を融合し、日本の節句文化を次代に継承してまいりましょう!
(文責・撮影) 専務理事 柴崎 稔



講演会「岩槻に於ける五節句の催し」講師:加藤三郎氏
平成30年4月25日(水)弊会の4月理事会終了後、岩槻の「料亭ほてい家」にて「岩槻に於ける五節句の催し」と題して講演会が開催されました。講師には、NPO法人 岩槻人形文化サポーターズ 代表 加藤三郎氏をお迎えし、ご講演頂きました。NPO法人 岩槻人形文化サポーターズは、2020年開館予定の岩槻人形博物館を通して、岩槻の人形文化や歴史を広く発信し、次の世代に引き継ぐことをミッションとして、岩槻の地域アイデンティティの醸成活動や岩槻の様々な団体をつなぐ活動を行う目的で設立された団体です。現在活動をされている内容の1つとして、岩槻の町を会場として 五節句(人日の節句、上巳の節句、端午の節句、七夕の節句、重陽の節句)にイベントを開催し、『観る』『創る』『食べる』ことを通して、五節句の意義と大切さを知ってもらい地域活性化と文化継承に努めておられることをご紹介頂きました。節句文化を様々な角度から研究・活動し、如何にして後世にも残していけるか…を考えさせられる良いご講演を頂きました。講演後、岩槻人形文化サポーターズの皆様と懇親を深めるべく会が催されました。
(文責)広報委員会 小田洋史