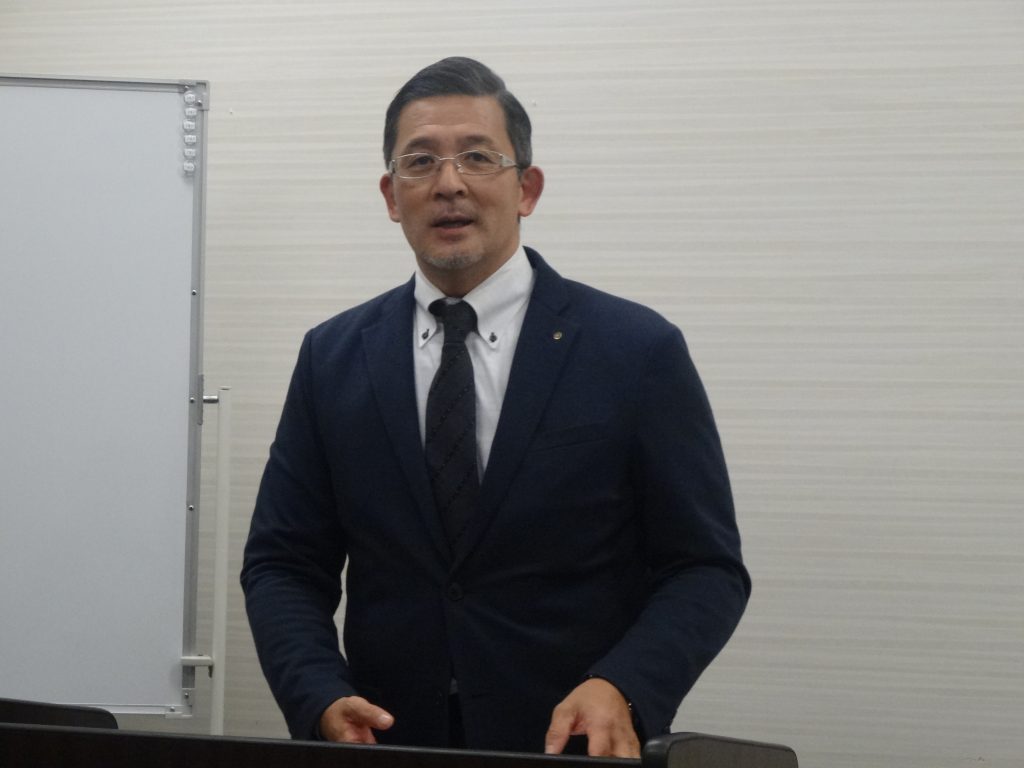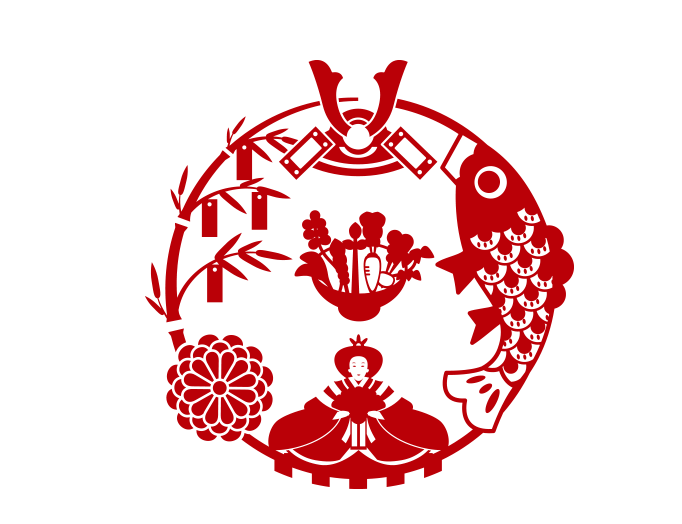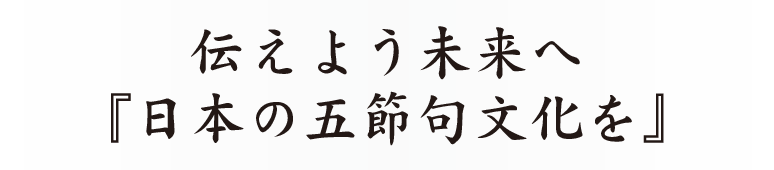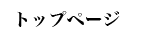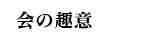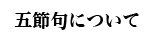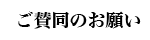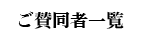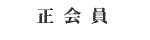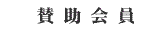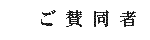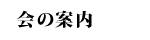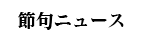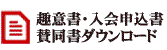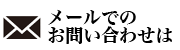ニュース
平成31年4月理事会
平成31年4月17日(木)、平成最後の4月理事会が東京 浅草橋にある東商センター会議室にて開催されました。
協議・審議事項では、(1)「日本博」イベント開催事業(案)、(2)令和元年度6月定時総会・理事会・研修会開催計画(案)、(3)節句文化継承若手プロジェクトチーム(仮称)全国ミーティング開催計画(案)について、(4)グローバル文化シンボル「こいのぼり」協会主催事業への当会の共催について、(5)平成30年度 事業報告・決算報告について、(6)令和元年度 事業計画(案)・予算(案)につて、(7)令和元年度 役員・組織改選について活発な協議がなされました。特に令和2年(2020年)5月から令和3年(2021年)3月までの開催予定の「日本博」イベントについては、内容について期限が迫っており、様々な意見や検討がなされ纏まることが出来ました。また、元号が令和になって初めてとなる定時総会も6月12日(水)と決まり、役員・組織改選の年でもある為、6月5日(水)に理事会を開催し確認することとなりました。
連絡報告事項として、内部広報誌 第2号 進捗報告がなされ、6月定時総会の案内と共に5月上旬に発送することが報告されました。
弊会は、業界のみならず行政や他組織・他団体と連携をしながら活発に活動をし、五節句が大切な日本の行事として、広く皆様に認知して頂けるよう今後も努めて参ります!
(文責)広報委員会 小田洋史


平成31年3月3日 上巳の節句(桃の節句)
3月に入りました。平成最後の3月3日の『上巳の節句』(桃の節句)となります。
『上巳の節句』は、日本の古い習わし「人形信仰」〔三月の初めの巳の日に人形(ひとがた)、あるいは形代(かたしろ)と呼ぶ草木・紙・ワラなどで作った人形で体を撫でて身のけがれや災いを移し、川や海に流した習わし〕と中国の『上巳の節句』とが結びついたものです。中国ではこの日、桃花酒を飲む習慣がありました。これは桃に邪気を祓う力があると信じられていたことから桃の節句とも呼ばれるようになりました。江戸時代から現在まで日本では雛人形を飾る「ひな祭り」という日本固有の人形文化があります。雛人形は、「人形信仰」の行事と、平安時代の宮中の幼い姫たちの人形遊び(ひいな遊び)とが、長い間に結びついたのが起源と伝えられています。雛人形には、女児の健やかな成長を願い、その子の身代わりとなって厄災を引き受ける厄払いの意味もあるのです。
年に一度のお祝いの日です。雛人形を飾り、白酒・菱餅・あられ・桃の花等を供え、お祝い膳を囲み、家族や親類が揃ってお祝いをしてみてはいかがでしょう。
(文責)広報委員会 小田洋史

第二回 節句予祝の会 開催
2月13日18時より、愛知菓子会館3階におきまして「第二回節句予祝の会」を開催いたしました。前回決議した内容より、「予祝」「直来」を一般に知ってもらう取り組み、起縁プロジェクトの活動報告を行い、取り組みをしてみて良かったことや悪かったことを取り纏め、より良い今後の展開について話し合いました。次回は5月中旬に開催する予定です!!皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
(文責) 総務委員会 岡崎 拓


平成31年1月7日 人日の節句
年が明けて三が日が過ぎ、今年もいよいよこの節句が参りました!
そう!1月7日は『人日の節句』です。
『人日の節句』は、正月の終わりが六日で新年の始めが七日ということから、この日は一年の始めの節日(季節の変わり目の日)とされていました。昔、中国ではこの日に七種菜の汁を食して無病息災を祈願しました。これが日本古来の「正月七日のお祝い・七草粥」に通じ、『人日の節句』として定着しました。七草とは、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの七つの野草となります。
七草粥を食べる理由はたくさんありますが、自然界から新たな生命力をもらい、無病息災健康来福を願い、邪気を払うと言われています。冬に不足しがちな野菜をお粥に入れ食べていたともされ、江戸時代から大切な行事でした。最近では、お正月に食べすぎて疲れた胃腸をいたわり、ビタミンを補う効果もあるとも言われています。
是非、この機会に食べて一年間の無病息災健康来福を願いましょう!
(文責)広報委員会 小田洋史

平成31年 新年のご挨拶
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
初詣や凧あげ、羽根つき、一般的だった正月行事も多様化する環境の中で、外食や、コンビニ、量販店など休まず営業する施設も増え、正月の過ごし方も随分と変化しておりますが、昨今の慌ただしい生活から少し離れ、正月気分を満喫され日本の新春をお過ごしください。
まもなく迎える人日の節句、移り変わる季節と共に行われる上巳の節句や、端午の節句、七夕の節句、重陽の節句。今年も日本独自の五節句文化に触れ合いながら穏やかな年となりますようお祈りしております。
私たちは、礼儀正しく、何時までも誇れる日本人の育成と、その一翼を担う五節句文化を未来に残すために邁進いたします。
皆さま方には、これからも、五節句文化の継承活動に、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
平成31年元旦
一 般社団法人 日本の節句文化を継承する会
会長 徳永深二


研修会「知っておきたい相続と事業継承のキホン」 講師:細野達男氏
平成30年12月11日(火)弊会の12月理事会終了後、講師として有限会社マルタツ 代表取締役 細野達男氏をお迎えし、「知っておきたい相続と事業継承のキホン」と題し、日本人形協会 埼玉支部の皆様と共に研修会が開催されました。
講師の細野達男氏は、有限会社マルタツの代表取締役を務められ、NPO法人首都圏定期借地借家権推進機構認定定借プランナー(上級職)、NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員で上級アドバイザーでもあられます。もともとはJAでの相続問題専門の部署に勤務されていたそうです。研修会では8パターンの家族構成の実例を基にご講演して頂きました。節税と分割は違いうということ。信託は銀行などでも出来るが自分や家族でも出来る。対策としてどの様にしておけば良いのか。色々なパターンがあることも教えていただきました。大切なことは、まず戸籍をよく調べておくこと。ハンコ代は支払える金額以内にしておくこと。遺言書を作成しておくこと。子どもがいなければ遺言書を作成し、相続人を決めておくこと。相続人を決めておくことで相続をスムーズに進めることが出来る。相続放棄が出来るのは、亡くなってから3か月ではなく、亡くなったことを知ってから3か月以内までなら相続放棄出来る。借金も財産であること。遺言書は法務局に預けることも出来る。などなど私たちが今後必ず経験するであろう相続のことを楽しく分かりやすくご説明いただき大変勉強になった研修会でした。
(文責)節句文化研修委員会 岸本和豊